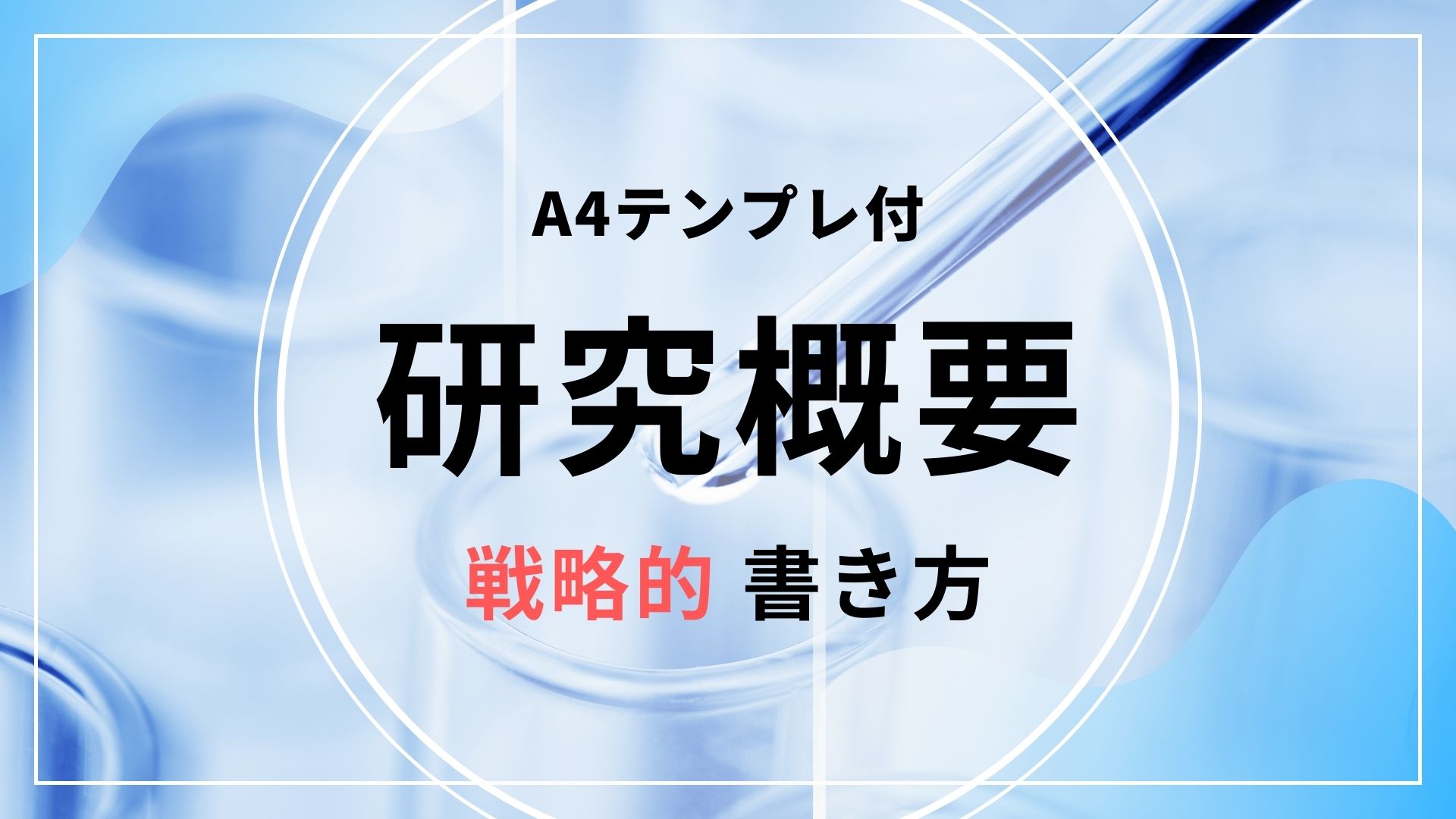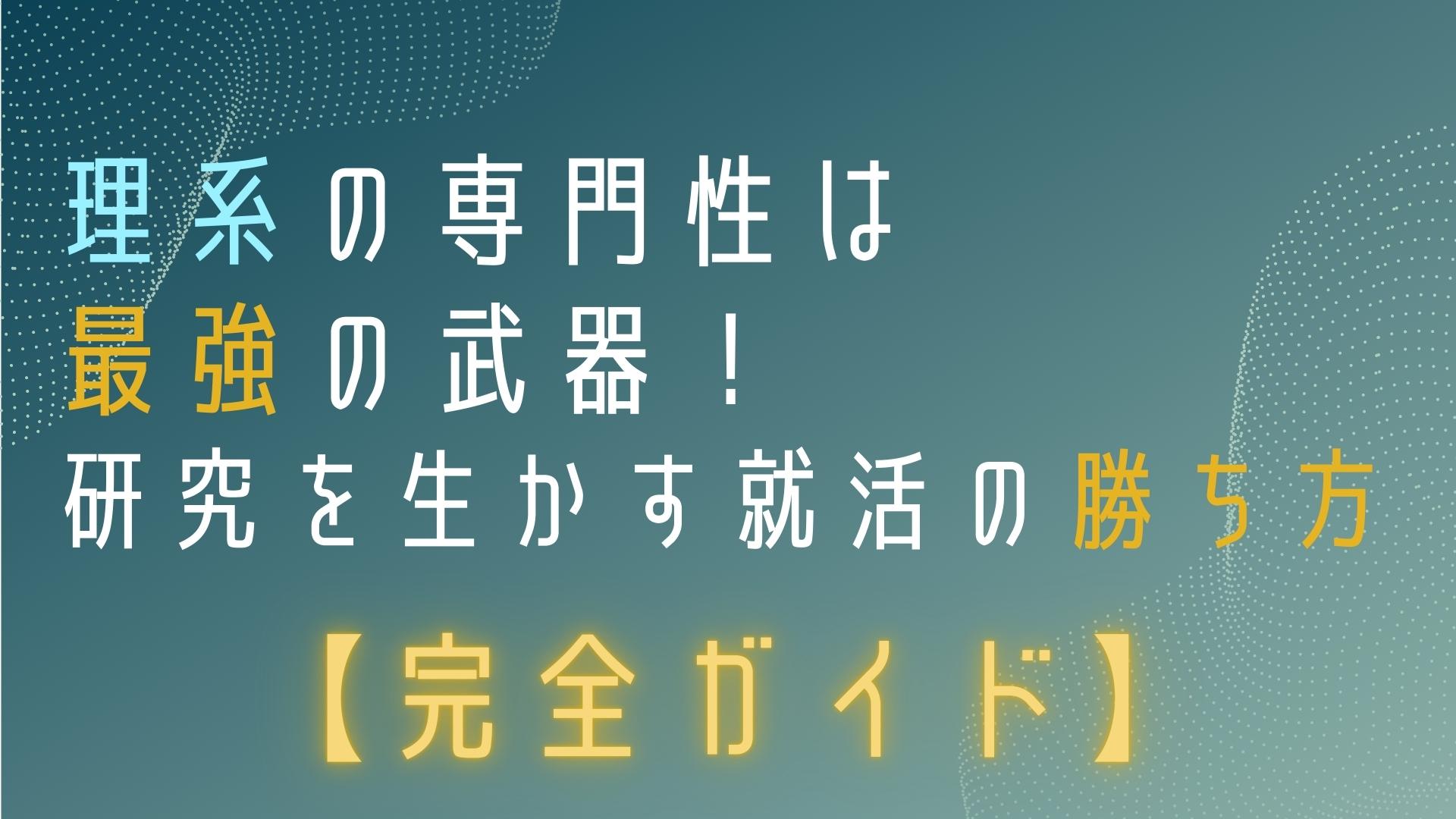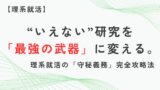「自分の研究、専門外の人事にどう伝えれば響くのだろう…」 「まだ結果も出ていないのに、一体何を書けばいいんだ…?」
理系就活における最重要書類の一つ、「研究概要」。
書き方一つであなたの評価は大きく変わりますが、守秘義務や進捗状況など、理系学生特有の悩みが尽きないのも事実です。
本記事では、単なる書き方のテクニックではありません。
人事担当者が「この学生に会いたい」と感じる戦略的なアピール術を、A4のテンプレートと、元院生のリアルなビフォー・アフター例文付きで徹底解説します。
さらに、「まだ研究が終わっていない」「守秘義務が不安」といった、多くの学生が抱える疑問にも明確な答えを提示。
この記事を読めば、あなたの研究概要は単なる「説明書」から、論理的思考力を示す「最高のプレゼン資料」へと変わります。
さあ、あなたの研究を最強の武器に変えましょう。
【あわせて読みたい】 本記事では『研究概要』の書き方に特化して解説しますが、そもそも理系就活の全体像や、多様なキャリアパスについて知りたい方は、まずはこちらの完全ガイドをご覧ください。
書く前に確認:研究概要の「守秘義務」と公開範囲のルール

素晴らしい研究概要を書き上げる前に、絶対にクリアすべき重要な点があります。
それは「この内容は、外に出していい情報なのか?」という守秘義務の問題です。
特に、企業との共同研究や、特許出願を控えた研究を行っている場合、情報の取り扱いには細心の注意が必要になります。
「知らなかった」では済まされないトラブルを未然に防ぎ、安心して就職活動に臨むために、以下のポイントを必ず確認してください。
指導教官に必ず確認すべきことリスト
まずは、あなたの研究を最も深く理解している指導教官に、以下の点を確認しましょう。
メールや口頭ではなく、記録が残る形で確認するのが理想です。
- 共同研究の有無:「この研究は、特定の企業や機関との共同研究ですか?その場合、情報公開に関する規定はありますか?」
- 特許出願の予定:「この研究内容について、特許を出願する予定はありますか?ある場合、どの情報をどの程度まで公開して良いですか?」
- 公開可能な範囲:「就職活動で研究概要として企業に提出するにあたり、公開してはいけないデータや技術はありますか?」
企業の特許情報を侵害しないための注意点
あなたの研究が、他社の特許技術を利用したり、関連したりするケースもあるかもしれません。
意図せず他社の権利を侵害してしまうことがないよう、「自分の研究は、〇〇という既存の技術を基に応用したものです」といった背景を正直に、かつ敬意を払って記述することが大切です。
面接などで深掘りされた際に誠実に答えられるよう、関連する先行研究や特許については、改めて整理しておきましょう。
どこまで書いて、どこからぼかすべきか?
指導教官への確認の結果、「全てを具体的に書くのはNG」という指示を受けることもあります。
その場合は、研究の「本質」は変えずに、具体的な「固有名詞」や「数値」をぼかすテクニックを使いましょう。
【ぼかし方の具体例】
- 化合物名・物質名
- 具体的すぎる例:「〇〇(具体的な化合物名)を合成した」
- ぼかした例:「高い発光特性を持つ、新規の有機EL材料を合成した」
- 具体的すぎる例:「〇〇(具体的な化合物名)を合成した」
- 共同研究先の企業名
- 具体的すぎる例:「〇〇社(企業名)から提供された触媒を用いた」
- ぼかした例:「国内大手化学メーカーと共同開発した触媒を用いた」
- 具体的すぎる例:「〇〇社(企業名)から提供された触媒を用いた」
- 具体的な数値データ
- 具体的すぎる例:「収率95.2%を達成した」
- ぼかした例:「従来法に比べ、収率を大幅に改善することに成功した」
- 具体的すぎる例:「収率95.2%を達成した」
このように表現を工夫することで、守秘義務を守りながらも、あなたの研究の価値や、あなたが発揮した能力を十分に伝えることが可能です。
【あわせて読みたい】
就職活動での守秘義務について徹底解説した記事はこちらから読めます。
そもそも「研究概要」で人事は学生の何を見ているのか?

研究概要を書き始める前に、一つだけ、絶対に知っておくべきことがあります。
それは、人事担当者のほとんどは、あなたの研究分野の専門家ではないということです。
彼らは、あなたの研究成果の学術的な価値を評価しているのではありません。
そうではなく、あなたの研究概要を「思考力とポテンシャルを測るためのケーススタディ」として読んでいます。
この大前提を理解するだけで、あなたの研究概要は劇的に変わるはずです。
研究内容そのものより「思考プロセス」が重要
人事が知りたいのは「何を研究したか(What)」という結果だけではありません。
それ以上に「なぜ、どのように、その研究に取り組んだのか(Why, How)」という、あなたの思考プロセスや人間性に強い関心を持っています。
- なぜその研究テーマを選んだのか?
- どんな壁にぶつかり、どうやって乗りこえたのか?
- その経験から何を学び、今後どう生かせるのか?
あなたの研究活動そのものが、入社後の仕事ぶりをイメージさせる、最高の自己PR資料なのです。
人事が評価する3つの力
具体的に、人事はあなたの研究概要から以下の3つの力を読み取ろうとしています。
- 課題設定能力: なぜその研究が必要なのか、社会や業界にどんな課題があったのかを正しく理解し、研究の「目的」を設定する力です。これは、ビジネスの世界で「顧客の課題を発見し、解決策を考える力」に直結します。
- 仮説検証能力: 設定した課題に対し、自分なりの仮説やアプローチを考え、実行し、失敗と成功を繰り返しながら粘り強くゴールを目指す力です。研究活動で最も重要なこの能力は、どんな仕事でも求められる普遍的なスキルです。
- 再現性(入社後の活躍イメージ): 研究活動を通じて得た学びやスキルが、入社後、その企業でどのように生かせるかを示す力です。研究と事業内容が直接関係なくても構いません。「粘り強さ」や「論理的思考力」といったポータブルスキルが、企業の課題解決にどう貢献できるかを伝えることが重要です。
これだけは押さえる!研究概要の基本構成と必須7項目
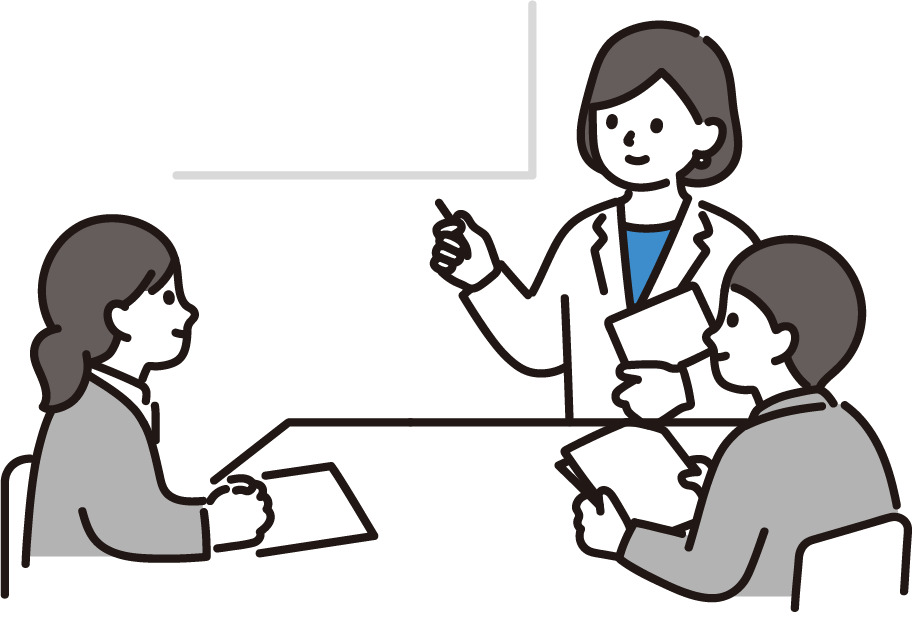
このセクションでは、あなたの思考プロセスを効果的に伝え、人事担当者をひきつけるための「型」となる基本構成を解説します。
この順番で書き進めるだけで、誰が読んでも分かりやすく、論理的な研究概要を完成させることができます。
一つひとつの項目の「役割」を理解しながら、自分の研究内容を当てはめていきましょう。
研究テーマ:研究の「顔」を一行で定義する
最初に書く研究テーマは、あなたの研究概要全体の「タイトル」であり、読み手の第一印象を決定づける重要な要素です。
この一行であなたの研究の「面白さ」や「価値」を予感させることが、全体を好意的に読んでもらうための鍵です。
専門用語を並べるだけでなく、「どんな価値がある研究なのか」が一目で伝わるように工夫しましょう。
例: 〇 「〇〇(専門用語)に関する研究」
◎ 「〇〇(課題)を解決する、△△(技術)の開発」
研究背景:なぜ、その研究が必要なのか?
ここでは、あなたの研究が取り組む「課題」を提示します。世の中や学術分野において、どのような問題や未解決な点があったのかを簡潔に説明してください。
この「背景」を語ることで、あなたが社会や業界の動きに関心を持ち、目的意識を持って研究に取り組んでいることをアピールできます。
これは前述した「課題設定能力」を示す絶好の機会です。
研究目的:何を、どこまで明らかにするのか?
背景で示した課題に対し、「この研究で何をゴールとするのか」を明確に宣言する部分です。
研究の全体像を示す、道しるべの役割を果たします。
「〇〇を明らかにすること」「△△を開発すること」のように、具体的かつ簡潔に記述しましょう。
研究方法:どのようにアプローチしたのか?
設定した目的を達成するために、どのような実験や調査、分析を行ったのかを説明します。
ただし、専門的すぎる手順を詳細に書く必要はありません。
「どのような工夫をしたか」につながる、アプローチの「要点」を絞って記述するのがコツです。
【最重要】自分なりの工夫・独創性:あなたらしさが光る部分
この項目が、あなたの評価を大きく左右する最重要パートです。
テンプレート通りの研究内容ではなく、「あなただからこそ」の価値を示しましょう。
- どんな困難や予期せぬ問題がありましたか?
- その壁を乗りこえるために、どんな仮説を立て、何を試しましたか?
- 先行研究にはない、あなた独自のアプローチは何でしたか?
ここでの試行錯誤のプロセスこそ、あなたの「仮説検証能力」や、粘り強さ、問題解決能力を証明する最高の証拠です。
結果と考察:何が分かり、どう考えたか?
研究によって、どのようなデータや事実が得られたのかを記述します。
そして、結果以上に重要なのが「考察」です。
得られた結果から「何が言えるのか」「どのような意味があるのか」を、あなた自身の言葉で論理的に説明してください。
物事の本質を捉える分析力が試されています。
研究から得た学び:入社後にどう生かせるか?
研究概要の締めくくりです。
研究活動全体を通じて、あなたがどのようなスキルや能力を身につけたのかを具体的に言語化します。
そして、その学びが「入社後、企業の事業にどう貢献できるのか」を明確につなげてアピールしてください。
ここで人事担当者は、あなたが入社後に活躍する姿をイメージできるか(=再現性)を判断しています。
【応用編】「まだ結果がない」「研究途中」の場合の書き方
「まだ十分な結果が出ていない…」と不安に思う方もいるでしょう。
心配ありません。その場合は、「結果」ではなく「プロセス」に重点を置いて書きましょう。
- 結果・考察: 「現在までに〇〇という中間結果が得られており、当初の仮説の妥当性が示唆されています」
- 今後の展望: 「今後は△△というアプローチで検証を進め、最終的に□□を明らかにできる見込みです」
このように書くことで、計画性や将来性、そして現時点で分かっていることから論理的に思考する力をアピールできます。
【例文】人事はどこを見る?「平凡な説明」を「会いたい自己PR」に変える添削実例

ここまで解説した「構成」や「人事の視点」を、実際の例で見ていきましょう。
ここでは、ある化学系の大学院生が実際に提出した研究概要を基に、「ありがちな例(ビフォー)」と「人事に響く例(アフター)」を比較します。
どこをどう変えれば、評価が劇的に変わるのか。そのポイントをつかんでください。
【ビフォー】ありがちな「研究内容の説明」で終わった例
研究テーマ:新規π共役系分子の合成と物性評価
背景:π共役系分子は優れた電子材料としての応用が期待されていますが、従来の合成法では収率が低いという課題がありました。
目的:収率の高い新規合成法を確立し、その光物性・電気化学特性を評価することを目的としました。
方法:〇〇と△△を反応させ、□□を合成しました。
結果:目標化合物を収率XX%で得ました。この化合物は△△nmに吸収極大を示し、□Vの酸化還元電位を示しました。
学び:この研究を通じて、日々コツコツと実験をやり遂げる粘り強さを学びました。
【課題点】 学会発表や論文として見れば、客観的な事実を正確に記述した、模範的な書き方です。しかし、就職活動の「自己PR」という観点では、非常にもったいない書き方と言えます。事実を淡々と並べているだけで、研究の面白さや、本人の工夫が見えません。最後の「学び」も抽象的で、他の学生との差別化ができていません。
【アフター】人事が「会いたい」と思う、思考プロセスが見える例
研究テーマ:低コスト・高収率を実現する新規π共役系分子の合成ルート開拓
背景:次世代の電子材料として期待されるπ共役系分子ですが、その合成には高コストな貴金属触媒が必須であり、社会実装への大きな壁となっていました。
目的:私は、安価で豊富な鉄触媒を用いる新規合成法を確立し、製造コストを従来法の1/100に抑えることで、実用化への道を開きたいと考えました。
自分なりの工夫:当初、鉄触媒では反応が全く進行しませんでした。そこで20種類以上の添加剤や温度条件を組み合わせ、全ての失敗データを分析した結果、特定の保護基が反応を阻害しているという仮説を立てました。最終的には、合成ルートそのものを根本から見直すという大胆な方針転換に踏み切りました。
成果と学び:結果として、鉄触媒を用いた新規合成法で、従来法を上回る収率XX%を達成しました。この経験は、単なる合成成功以上のものを私にもたらしました。それは、数十回の失敗にも屈しない「粘り強さ」を土台に、既存の常識を疑い課題を再定義する「客観的・批判的思考力」を働かせ、最終的に新たな価値を創造する「実行力」へとつなげる一連の課題解決プロセスです。貴社の研究開発チームの一員として、この「前提を疑い、新たな視点を持ち込む力」を生かし、チームに化学反応を起こすことで、課題解決に貢献できると確信しております。
【改善のポイント】 背景に「コスト」というビジネスに近い課題を設定し、「鉄触媒」という具体的な解決策を提示。そして、最大のポイントである「工夫」で、失敗から仮説を立て、大胆な方針転換で成功に導いたプロセスを生き生きと描いています。最後の「学び」も、単なる感想ではなく、入社後の活躍をイメージさせる力強いアピールにつながっています。
まだやってる?評価を落とす「もったいない」研究概要、3つの落とし穴

せっかく素晴らしい研究をしていても、伝え方一つで評価を大きく下げてしまうのは非常にもったいないことです。
ここでは、多くの理系学生が書いてしまいがちな、評価されない研究概要の典型的な失敗例を3つ紹介します。
自分の研究概要がこれに当てはまっていないか、セルフチェックしてみましょう。
NG例1:専門用語のオンパレードで、読み手を置いてきぼりにする
最も多い失敗例がこれです。
学会発表と同じ感覚で、専門用語や化学式、略語を多用してしまうと、専門外の人事担当者は全く内容を理解できません。
内容が伝わらないばかりか、「相手の知識レベルに合わせて説明する能力が低いのかもしれない」と、コミュニケーション能力に懸念を持たれてしまう可能性すらあります。
【対策】 「文系の友人」や「高校生の自分」に語りかけるような気持ちで、できる限り専門用語を避け、平易な言葉に翻訳する努力をしましょう。専門知識のない相手に、物事の本質を分かりやすく説明する能力は、ビジネスの世界で極めて重宝されるスキルです。
NG例2:研究の「結果」だけを自慢し、プロセスが見えない
「収率〇〇%を達成」「△△という数値を記録」といった輝かしい結果は、もちろん素晴らしいことです。
しかし、その結果だけをアピールしても、人事担当者には響きません。
なぜなら、彼らが知りたいのは「その結果を出すまでに、あなたがどう考え、どう行動したか」というプロセスだからです。
結果だけでは、あなたの思考力や粘り強さは伝わりません。
【対策】 前述した「自分なりの工夫」の項目を、最も熱意を込めて書きましょう。どんな壁にぶつかり、どう試行錯誤し、どう乗りこえたのか。そのストーリーこそが、あなたという人材の価値を雄弁に物語ります。
NG例3:学びが曖昧で、企業への貢献意欲が感じられない
研究概要の締めくくりに、「この研究を通じて、探究心を学びました」「粘り強さが身につきました」とだけ書く学生は非常に多いです。
これは間違いではありませんが、あまりに抽象的で、他の学生との差別化ができません。
また、企業側からすると「で、その学びをうちの会社でどう生かしてくれるの?」という疑問が残ってしまいます。
【対策】 「学び」は、具体的な「スキル」として言語化し、必ず「企業への貢献」につなげましょう。「【〇〇という経験】から【△△という能力】を習得しました。この能力は、貴社の□□という事業で生かせます」というように、明確な形で入社後の活躍イメージを提示することが重要です。
まとめ
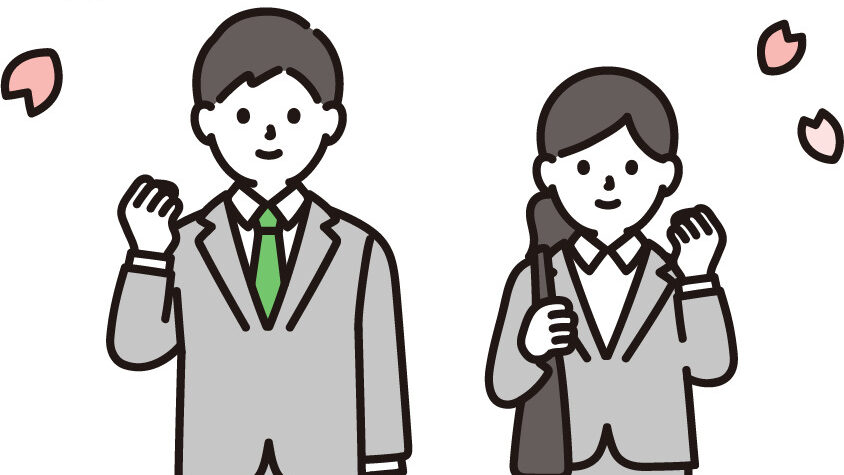
本記事では、理系就活における研究概要の戦略的な書き方を、人事の視点から具体的な例文やNG例を交えて解説してきました。
研究概要は、単なる「研究内容の説明書」ではありません。
それは、あなたという人材の「思考プロセス」と「ポテンシャル」を伝える、最高のプレゼンテーション資料なのです。
最後に、重要なポイントをもう一度確認しましょう。
- 人事の視点を理解する:評価されるのは結果だけでなく、課題解決までのプロセスです。
- 基本構成を守る:7つの必須項目に沿って書けば、論理的なストーリーが完成します。
- 「自分なりの工夫」を主役にする:あなたの価値が最も光る、試行錯誤の過程を具体的に語りましょう。
- 学びと貢献意欲をつなげる:身につけたスキルが入社後どう活きるかを明確に示してください。
まずはこの記事で紹介した「アフター」の例文やテンプレートを参考に、あなたの言葉で一度、研究概要を書き上げてみてください。
最初から完璧を目指す必要はありません。
手を動かして初めて、見えてくるものがあります。
もし、「一人で書くのは不安だ」「プロの視点から客観的なフィードバックがほしい」と感じたら、理系就活に特化した就活エージェントに相談するのも一つの有効な手段です。
彼らは数多くの理系学生のES添削や面接対策を行ってきた専門家です。
あなたの研究概要を、より企業に響く形に磨き上げる手助けをしてくれるでしょう。
あなたの研究活動は、間違いなくあなたの強力な武器です。自信を持って、その価値を伝えてください。
応援しています。